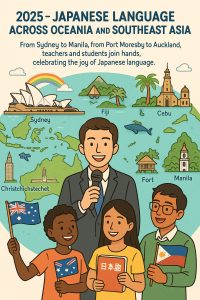 文部科学省の学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」がうたわれるなど、主体性の育成が求められているようです。しかし、現場では、具体的な手法が整っていないと聞きます。今日は、どうすれば「学習者主体の授業」「主体性・自主性を重んじる学び」が実現できるか考えてみました。
文部科学省の学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」がうたわれるなど、主体性の育成が求められているようです。しかし、現場では、具体的な手法が整っていないと聞きます。今日は、どうすれば「学習者主体の授業」「主体性・自主性を重んじる学び」が実現できるか考えてみました。
私は2002年から10年間、北京大学と清華大学で日本語授業を担当しました。毎回の授業を、前半はディスカッション形式、後半はコンテスト形式で行い、コンテスト後に優勝者がみんなに感謝を述べ、他の教え子たちは優勝者を祝福しました。私は教室の後ろからその様子を見守るだけで、講義形式で一方的に話すことはなく、すべての授業を学習者主体で進めました。もちろん、そこにはどんなテーマでも即興でスピーチできる「型」を教え子たちと作ったことも大きいのですが、彼らは、研究で有効性が証明される以前から、アクティブリコール(能動的想起)を自然に取り入れていて、間隔反復も身につけていたので、それを、私の授業や放課後の特訓でも使いました。こうした実践が「学習者主体」の授業を支えた具体例です。
その後の14年間は、世界各地を巡りながら、出会った多くの先生方や学習者から、学習を持続させる工夫や方法を学びました。
この経験を通じて、「教授法の改良」ではなく「学習法の活用」が、学習者主体授業実現の鍵だとわかりました。教師は「学びの方法をデザインする人」になることが大事だと思います。多様な学習法を学習者に試させ、自分に合った方法を見つけてもらい、その努力と成長を具体的に承認することで、学習者全員にピグマリオン効果を及ぼすことが可能になりました。
文科省が掲げる「学習者主体の教育」を実現させるため、学習法の普及・定着へ転換することが、持続可能で公平な教育を築く第一歩になると思っています。